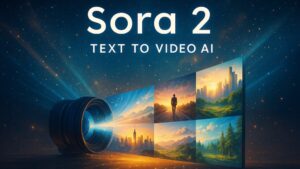この記事でわかること
中小企業でIT担当を任されている方の中には、「業務が多すぎて手が回らない」「専門知識がなくて不安」そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
そこで注目されているのが、情シス業務のアウトソースという選択肢。
この記事では、情シスアウトソースの基本的な考え方から、任せられる業務の例や導入時のポイントまでをやさしく解説します。
「ちょっと気になる」「うちにも使えるかも?」と思った方は、ぜひ読み進めてみてください。
情シスアウトソースとは?その意味と目的
「情シス業務」とはどんな仕事なのか?
情報システム部門、通称『情シス』は、社内のIT環境を支える縁の下の力持ちです。
パソコンやネットワークの管理、社員のアカウント発行、システムの導入支援、トラブル対応、セキュリティ対策など、『ITに関するあらゆる業務を担う、社内のITおまかせ係』ともいえます。
さらに実際の現場では、「Zoomの音が出ない」「プリンターが動かない」「メールが届かない」といったIT機器に関する『困りごと相談窓口』としての役割も自然と担わされているケースも多いのではないでしょうか。
本来の業務と直接関係ないトラブル対応にも時間を割かれがちで、気づけば1日が終わっていた…という状況も珍しくありません。
中小企業では、情シス担当が1人だけ、あるいは他業務と兼務しているケースも少なくないため、対応すべき内容に対して十分な体制を整えるのが難しく、現場では「やるべきことは多いのに、人が足りない」といった声も耳にします。
「情シスアウトソース」とはどんなものなのか?
アウトソース とは、ある業務や役割を社外の専門業者に委託することです。
情シス業務においては、パソコンやクラウドの管理、社員のITサポート、システム運用などの業務を『外部のパートナーに任せる』ことを指します。
「全部を任せなければいけないの?」と心配される方も多いですが、実際は必要な範囲だけを部分的に依頼できるサービスも提供されています。
たとえば、新入社員のPCセットアップだけ任せたい
社員からのIT問い合わせ対応だけサポートしてほしい
クラウド導入やセキュリティ設定だけ一緒に考えてほしい
といったように、自社でカバーしづらい部分だけを補完するような使い方も可能です。
継続的な支援はもちろん、「導入時だけ」「一定期間だけ」など、期間を区切って依頼することもできるため、「情シスの業務負荷が一時的に集中しているとき」だけアウトソースを利用するなど、柔軟に活用することができます。
なぜ今、情シス業務の外部化が注目されているのか
すこし前までは「ITまわりは社内でなんとかするもの」という考え方が一般的でした。
しかし近年では、情シス業務の一部または全部を外部パートナーに委ねる『アウトソース』という選択肢が、徐々に注目を集めるようになっています。
その背景には、次のような変化があります。
IT環境の複雑化(クラウド、リモート、セキュリティ対策などが増加)
ひとり情シスや兼務体制の定着化(リソース不足の長期化)
DXや働き方改革で、ITに期待される役割が広がっている
IT人材の採用難・コスト増加により、内製対応が難しくなっている
こうした状況により、「トラブル対応に追われる毎日から抜け出せない」「仕組みづくりや改善提案に時間が割けない」といった声が増えてきました。
そこで注目されているのが、社内のIT担当者を支えてくれる外部パートナー という存在です。
すべてを外注するのではなく、足りないところだけ補完する『共創型』の支援が可能なため、無理なく導入できるのも支持されている理由のひとつです。
中小企業におけるアウトソース活用の広がり
ひとり情シス・兼務担当の増加
中小企業では、専任の情シス担当を確保すること自体が難しいケースが少なくありません。
現場では『ITに詳しいから』という理由で、担当業務以外に情シス業務を兼任することも多く、いわゆる「ひとり情シス」「ゼロ情シス」と呼ばれる状態になっている企業が多くあります。
こうした体制では本来の業務との板挟みで十分な対応が難しくなるだけでなく、情報セキュリティやトラブル時のリスク対応にも不安が残るのが実情です。
情報システムの複雑化と属人化リスク
クラウドの活用、テレワーク環境の整備、さまざまなSaaSの導入など、中小企業のIT環境はここ数年で一気に高度化・多様化しています。
にもかかわらず、管理・運用を担う人員やナレッジが追いつかず、『属人化』が進行してしまっている現場も少なくありません。
「その作業はあの人しかできない」「設定内容が誰にも分からない」こうした属人状態は、担当者の異動や退職が発生したときに、企業全体のIT環境に影響が及ぶ重大リスクとなり得ます。
「あの人しか知らない設定がある…」そんな属人化の兆候、ありませんか?
専門家に相談するだけでも、改善のヒントが見えてくるかもしれません。
「社内だけでは難しい」と感じる企業が、アウトソースを選び始めている理由
こうした背景から、「社内対応だけでは立ち行かなくなってきた」と感じる中小企業が増えています。
業務改善の必要性を感じながらもIT施策まで手が回らなかったり、新しいツールを導入したくても設計や検証の時間が取れなかったりといった課題がよく見られます。
また、「セキュリティに不安はあるけれど、何から備えればいいのか分からない」という声も少なくありません。
このように、『必要性は感じているけれど、対応する時間も知識もない』という悩みは、多くの企業に共通するものとなっています。
こうした現実をふまえ、アウトソースの導入を検討・実施する企業が少しずつ増え始めているのです。
どんな業務をアウトソースできるのか?
「アウトソース=全部丸投げ」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、実際は『日常業務の一部だけを柔軟に任せるスタイル』が主流です。
ここでは、よく中小企業で委託されている業務の具体例をご紹介します。
PC・アカウント管理など、日常のIT業務をサポート
新入社員のパソコンセットアップやアカウント発行、ライセンス管理など、毎月のように発生するルーチン作業を外部に任せることで社内の負担を大きく軽減できます。
特に中小企業では、「対応できる人が限られていて、タイミングによって業務が滞る」といった課題も多いため、手の足りない部分のみを支援してもらう活用法が広がっています。
社内のITトラブル&ヘルプデスク業務をリモートで対応
「パソコンが起動しない」「ネットワークにつながらない」「メールが届かない」などのITトラブルや問い合わせ対応は、情シス業務の中でも時間を奪われやすい業務です。
こうした業務を外部のサポート窓口がリモートで対応してくれる体制を整えれば、社内からの『困りごと』にスピーディーかつ安定して対応できるようになります。
テレワーク・クラウド導入を支える「リモート環境構築支援」
テレワーク対応やクラウドサービスの導入を進める中で、「社内だけでは対応しきれない」と感じる企業も多いようです。
特にVPNやリモート接続の環境整備、クラウド導入における設計・初期設定、さらにアクセス制御やセキュリティ設定など、専門知識が求められる工程では外部の支援が有効に機能します。
自社の負担を最小限に抑えながら、安全かつ確実に導入を進められるのが大きなメリットです。
社内会議や研修など、オンライン業務の支援にも対応
オンライン会議や社内研修、ウェビナーなど、動画や配信に関わる業務も、アウトソースが活用されるシーンのひとつです。
配信機材の選定・設置、操作サポート、ライブ配信の立ち合いなど、自社ではノウハウや人手が不足しがちな部分をプロに任せることで、社内イベントの質を保ちつつ担当者の負担を減らすことができます。
導入パターンと注意すべきポイント
自社に合う支援スタイルを選ぶ
情シス業務のアウトソースは、会社ごとの課題や体制に応じて、部分的・段階的に導入できる柔軟なサービスが増えています。
たとえば「PCのセットアップだけ」「社員からの問い合わせ対応だけ」など、特定の業務に特化した支援を提供している企業もあり、必ずしも大規模な外注から始める必要はありません。
まずは「どの業務が特に負担になっているか」「どこを補完してもらうと業務がラクになるか」といった視点で、自社に合ったアウトソースの入り口を見つけることがポイントです。
委託する範囲と責任分担を、事前にしっかり整理する
アウトソース導入を成功させるには、「どこまでを自社で対応し、どこからを外部(委託先)に任せるのか」を事前に明確にしておくことが重要です。
トラブルが起きたときの一次対応は社内で行うのか、それとも外部に直接連絡を入れるのか、といった役割とフローのすり合わせを曖昧にしたまま進めると、混乱の原因になる可能性が高いです。
導入前には対応業務をリストアップして範囲を整理し、緊急時の連絡体制などについても具体的な内容で共有・確認しておくことが安心です。
アウトソースは「任せきり」ではなく、「共に進める」パートナーとの協業です。
「自社に合うか不安」「どこから始めるべき?」そんなお悩みも一緒に整理します。
社内と外部の“役割分担”がスムーズな運用につながる
アウトソースは“社内の代わり”ではなく、社外の信頼できるパートナーとして一緒に業務を支える存在です。
うまく導入されている企業ほど社内と外部の連携がスムーズで、情報の共有や意思決定が滞りにくく、結果として安定した運用につながっているようです。
定期的なミーティングを設けたり、簡単な運用マニュアルを共有したりするだけでも、「誰が・何を・どう判断するか」が明確になり、トラブルが起きたときの対応も円滑になります。
一方的に「任せる」のではなく、「共に進める意識を持つ」ことがアウトソースをうまく活かすカギになります。
情シスアウトソースを検討するときの『はじめの一歩』
「負担になっている業務」を洗い出してみる
アウトソースを検討するとき「どこから手をつけたらいいのか分からない」と感じたら、まずは日々のタスクの中で時間がかかるもの・自分しか対応できないもの、をリストアップしてみましょう。
たとえばPCの初期設定や問い合わせ対応、資料づくりのサポートなど、もし誰かに任せられたら楽になる作業がきっといくつか見つかるはずです。
こうした内容を棚卸しすることで、アウトソースの検討に役立つだけでなく、社内の仕事の進め方そのものを見直すきっかけにもなるでしょう。
まずは「小さく試す」のもひとつの方法
アウトソースは何も最初から大がかりに導入する必要はありません。
最初は期間や範囲を限定して試してみる、という感覚で導入してみるのもおすすめです。
特に中小企業では「まずは一部の業務だけ委託してみる」といった、段階的な導入が選ばれることも少なくありません。
こうしたスモールスタートであれば、業務の引き継ぎや社内調整の負担も少なく、自社にとって本当に合っている支援内容かどうかを見極めることもできます。
結果として、「ここは外部にお願いした方が効率的」「この業務は社内で継続した方がよさそう」といった判断材料も得られやすくなります。
外部のパートナーに相談するだけでもヒントが得られる
「アウトソースを検討しているけれど、うちに合うかどうか分からない」「そもそも何を相談していいのか分からない」そう感じている方も多いかもしれません。
そんなときは外部パートナーに、自社の状況や今困っていることをざっくばらんに話すだけでも、プロの視点から課題整理や解決のヒントをもらえるケースが多くあります。
「この業務は任せられるかも」「このやり方は見直せそう」といった気づきは、第三者に話すことで初めて見えてくることも少なくありません。
導入を決める前提でなくてもOK。
『情報収集の一環』として相談してみるだけでも、なにか前に進むきっかけになるかもしれません。
まとめ
この記事ではアウトソースの基本的な考え方から、任せられる業務の具体例、導入前の整理ポイントまでを幅広くご紹介しました。
まずは「今困っていること」を洗い出し、外部の支援の活用を選択肢として持つことで、これまで手が回らなかった業務改善やIT活用が少しずつ前に進み始めるかもしれません。
このあと続く記事では、実際のメリットや選び方、導入時の注意点など、より実践的な内容をご紹介していきます。
ぜひ自社に合った活用方法を、少しずつ探っていきましょう。
専任のIT担当がいない、あるいは他業務と兼任でITも任されている——。
そんな“ゼロ情シス”“ひとり情シス”の状態で、日々奮闘している方も多いのではないでしょうか。
ePla運営会社では、PCやネットワーク環境の整備、クラウド導入、
日常のITトラブル対応まで、社内のIT業務をトータルでサポートしています。
「とりあえず何を見直せばいい?」という段階からでも大丈夫。
無料でご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。