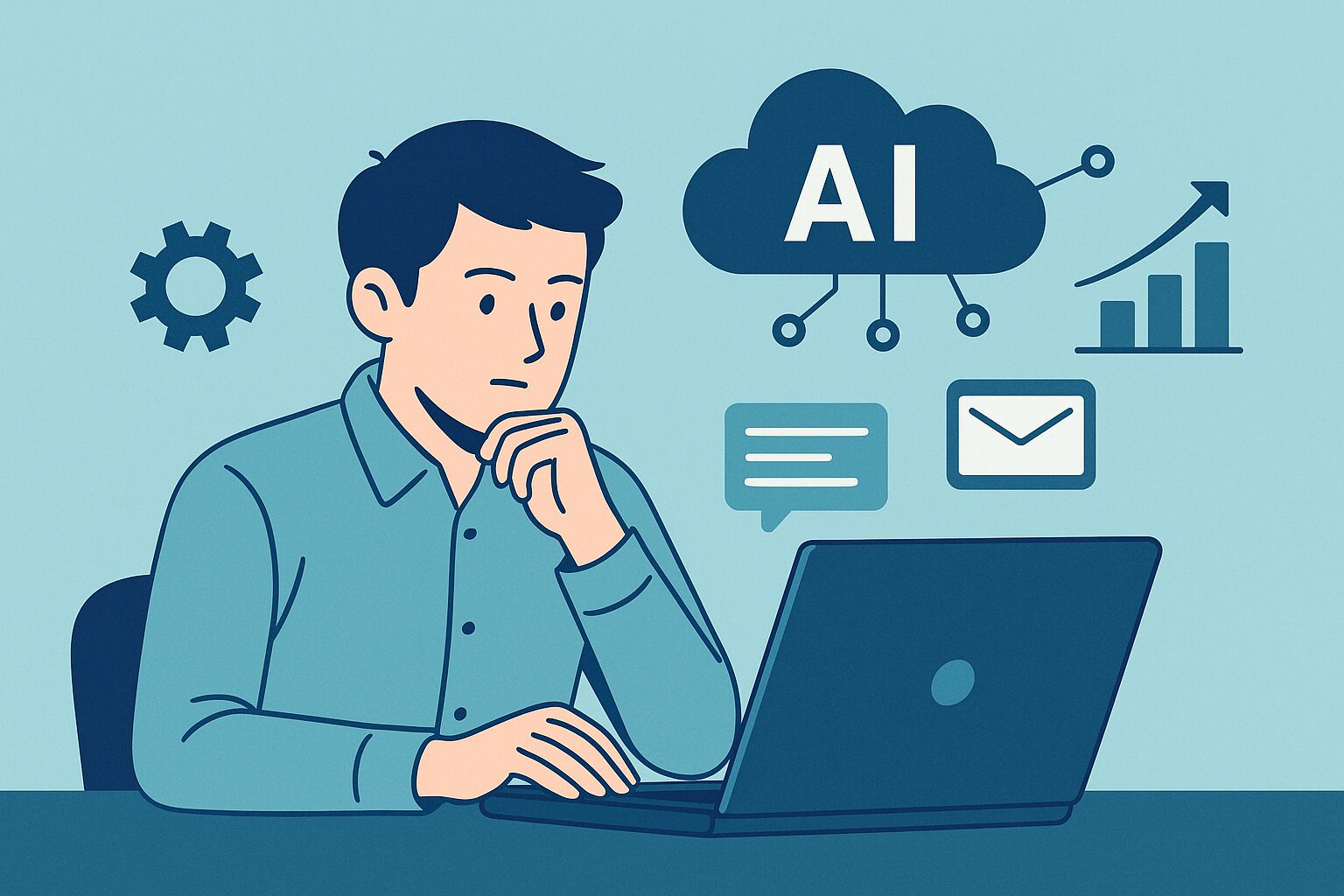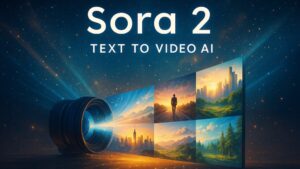この記事でわかること
情シス業務とAIは「相性がいい」理由
情報システム担当者の業務には、定型的で繰り返し発生する作業が数多く存在します。
加えて、社内のITサポート業務や各種ツール・システムの調査、ナレッジ共有といった、属人化しやすく負担の大きい業務を抱えているケースも少なくありません。
こうした状況下において、ChatGPTなどの生成AIをはじめとするAIツールは、一定の業務負荷を軽減する手段として注目を集めています。
例えば以下のようなケースです。
- 社内からのよくある問い合わせ対応文の作成(メールやチャットの下書き作成)
- システムマニュアルや社内向けのQ&Aなど、ナレッジの文書化・整備
- ツールやサービスの調査、比較検討資料のたたき台作成
AIはこうした「時間はかかるけれど、人が対応しなくてもよい業務」を効率よく処理するのが得意です。
そのため人手や時間が限られている中小企業や“ひとり情シス”の現場でも、心強いサポーターとして業務を支える選択肢のひとつとなるでしょう。
AI導入、まず試すべき3つのステップ
AIの可能性に興味はあっても、「何から始めればいいのか分からない」「検証にかける時間がない」そう感じて手を付けられていない方も多いのではないでしょうか。
特に兼務担当者などでリソースが限られている場合には、「無理なく始められて、効果を実感しやすい」導入ステップを踏むことが重要です。
ここでは、AI導入のファーストステップとして有効な3つのアプローチをご紹介します。
ステップ1:業務を「見える化」する
まずは、日々の業務の中で「時間がかかる」「繰り返しが多い」「属人化している」ものを洗い出してみましょう。
対象を明確にすることで、AIが “代わりにできる可能性が高い業務” が見えてきます。
とはいえ、業務の棚卸しにまとまった時間を確保するのが難しい場合もあるかもしれません。
そんなときは、日々の業務をこなしながら、「この作業はAIに任せられるか?」と意識的にチェックする習慣をつけるだけでも効果的です。
簡単でもメモしておくことで、自然と“AIに置き換えやすい業務”のリストが蓄積されていきます。
是非試してみてくださいね。
ステップ2:無料ツールを「触ってみる」
まずは無料で試せるAIツールを実際に触ってみましょう。
ここでは利用者が多く、使いやすいと評価されている代表的なAIツールを3つご紹介します。
いずれもアカウント登録と基本操作だけで、手軽に試せるものばかりです。
- ChatGPT(無料版):メール文作成、FAQ文の下書き生成など
- Bing AI(Edgeブラウザ):調べ物+文章生成がまとめてできる
- Perplexity AI:情報を検索しながら、要点を自動でまとめてくれる
いきなり本格導入を目指す必要はなく、まずは短時間でも触ってみることで「これ、意外と使えるかも?」という気づきが得られるはずです。”何ができるのか” を体感することが、導入への第一歩になります。
それぞれの特徴やおすすめの使い方は、下のパートで詳しくご紹介します。
ステップ3:小さな成功を“見える化”する
AIツールを使ってみて少しでも効果を感じることがあれば「なんとなく便利だった」で終わらせず、できるだけ具体的に “見える化” しておくことが大切です。
忙しい日々の中で、成果が実感しづらいと継続のモチベーションが下がりがちです。
しかし、たとえ小さなことでも「AIのおかげで助かった」という経験を記録しておくことで、活用の方向性や価値が見えやすくなります。
例えばこんなメモ
こうした“小さな変化”を積み重ねていくことで、「AIでの代行が適している業務」「AIでの代行が適していない業務」が把握できるようになっていきます。
社内に説明・共有する際にも “活用の実例”として使える材料” にもなるでしょう。
まずは「少し時短できた」「ちょっと楽になった」ことに気づき、残しておくことから始めてみましょう。
無料で試せる!おすすめAIツール3選
本サイトではこれまでにChatGPTやPerplexityの活用方法を紹介してきましたが、今回はそれらも含めて
「無料で試せる」「業務に役立てやすい」という視点から、代表的な3つのAIツールをピックアップしました。
いずれもユーザー数が多く、基本操作だけで手軽に使えるため、AIの “お試し導入” にぴったりです。
ChatGPT
OpenAIが開発した、自然なやり取りで文章やアイデアを生成できる対話型AIツールです。
「メール文を作って」「この文章をやわらかくして」など、指示をチャット形式で伝えることで、自動で文章を整えてくれるのが特長です。
たたき台やドラフト作成の場面で特に重宝し、自分の考えを整理したいときの“壁打ち相手”としても活用できます。
🛠 おすすめの使い方例 🛠
・社内向けメール文や案内文の下書き作成
・FAQやマニュアル文のたたき台作り
・自分の考えを整理したいときの壁打ち相手として使う

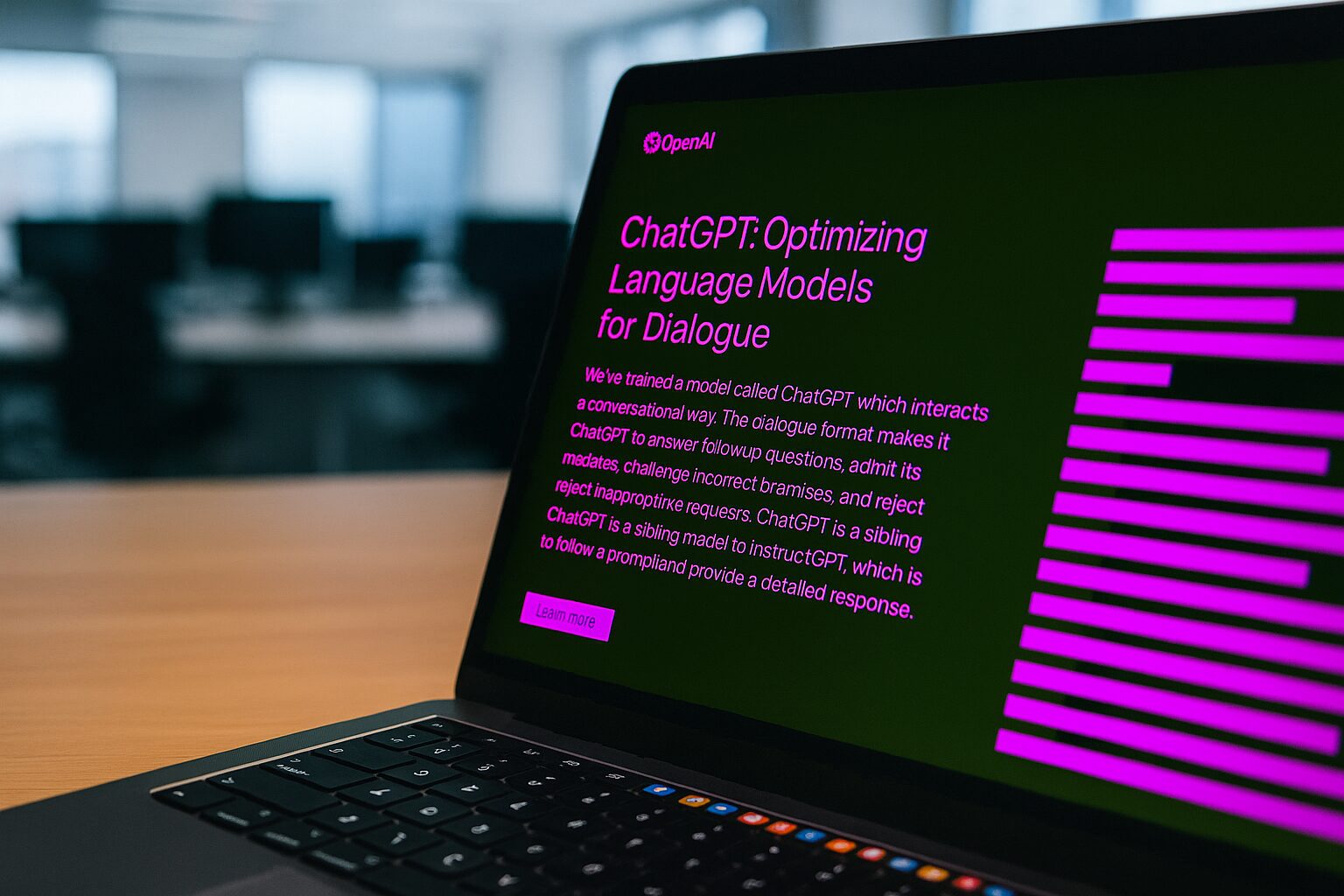
Bing AI
Microsoftが提供する、検索と生成AIを組み合わせたハイブリッド型のツールです。
Edgeブラウザ上で利用でき、調べ物をしながら、そのまま文章や要約を生成できるのが大きな特長。
ブラウザの延長線上で使える手軽さがあり、「調査→整理→文書化」の一連の流れをスムーズに進めたい場面に役立ちます。
🛠 おすすめの使い方例 🛠
・ツールの比較検討の下調べに
・資料作成のための事例やデータ探し+要約
・調べた内容をすぐにメール文などへ展開したいとき
Perplexity AI
Perplexityは、検索型AIに特化し、質問に対して信頼性の高い情報を整理・要約して返すのが特徴です。
回答には情報元のリンクも付与されるため、調べた内容の裏付けがしやすく、リサーチや資料作成の土台づくりに役立ちます。
「情報をまとめて把握したい」「短時間で要点をつかみたい」といった場面に特に適しています。
🛠 おすすめの使い方例 🛠
・自分が知らない分野の基礎知識をざっくりつかむ
・複数の情報をまとめて要点整理したいとき
・会議や提案資料づくりの“最初の材料集め”に使う

いろいろ試したい方には「ChatHub」もおすすめ
ChatHubは、複数のAIチャットツールを一つの画面で切り替えて使えるChrome拡張機能です。
「ChatGPT」「Bing」「Claude」「Gemini」など、代表的な生成AIをまとめて使い比べることができ、それぞれの違いや相性を確認しながら活用したい人にとって非常に便利です。
🛠 おすすめの使い方例 🛠
・複数のAIを同時に比較したいとき
・同じ質問に対する各AIの回答を並べて検討したいとき
・AIごとの特徴や違いを理解したいとき

AI導入をスムーズに進めるために – つまずきを防ぐ3つのポイント
AIツールはとても便利な一方で、使い始めの進め方によっては「思ったより活用できなかった…」と感じることもあるかもしれません。ここでは、そうしたつまずきを防ぐためのポイントを3つに整理してご紹介します。
「せっかくなら全社的に使いたい」と考えたくなるところですが、まずは自分の業務に取り入れてみて、効果を実感するところから始めるのがおすすめです。
実際の活用事例を少しずつ社内に共有していくことで、自然に関心や理解が広がりやすくなります。
「話題だから」「便利そうだから」で選んでしまうと、実際の業務でどう使えばいいか迷ってしまうことがあります。
AIツールは、解決したい課題や使いたい場面が明確になっていると、より効果的に使えます。
はじめてAIを使うと、「もっと自然な文章が出てくると思ってた」「手間が減ると思ったのに」と感じることもあるかもしれません。でも、AIは“たたき台”や“下書き”をつくるサポーターとして活用するのが基本です。
最初から完璧を目指すのではなく、“おおまかな部分をAIに任せて、仕上げは自分で整える”くらいの感覚がちょうどよく使いこなせます。
ワンポイントまとめ
小さく試して → 効果を実感して → その実例を少しずつ広げていく。
この流れを意識することで、無理なく、でも着実にAI活用を進められます。
まとめ
AIの活用は、特別な知識がある人だけのものではありません。
むしろ日々の業務に忙殺されている情シス担当者こそ、AIを「自分の味方」として活用するメリットが大きい分野です。
AIを使うことで、少しでも「考える時間が減った」「資料作成が楽になった」など、日々のストレスを減らせるチャンスが増えていきます。
小さな一歩が、これからの働き方や業務効率を大きく変えるかもしれません。
今日から、自分のためにAIを“ちょっとだけ使ってみる”ことから始めてみませんか?
ePla運営会社では、中小企業の現場に即したAI・ITツールの選定や活用方法について
無料でご相談を承っています。
「業務のどこにAIを取り入れられる?」「何から始めればいい?」といった段階からでも大丈夫です!
気軽に話せる“導入前相談窓口”として、ぜひご活用ください。