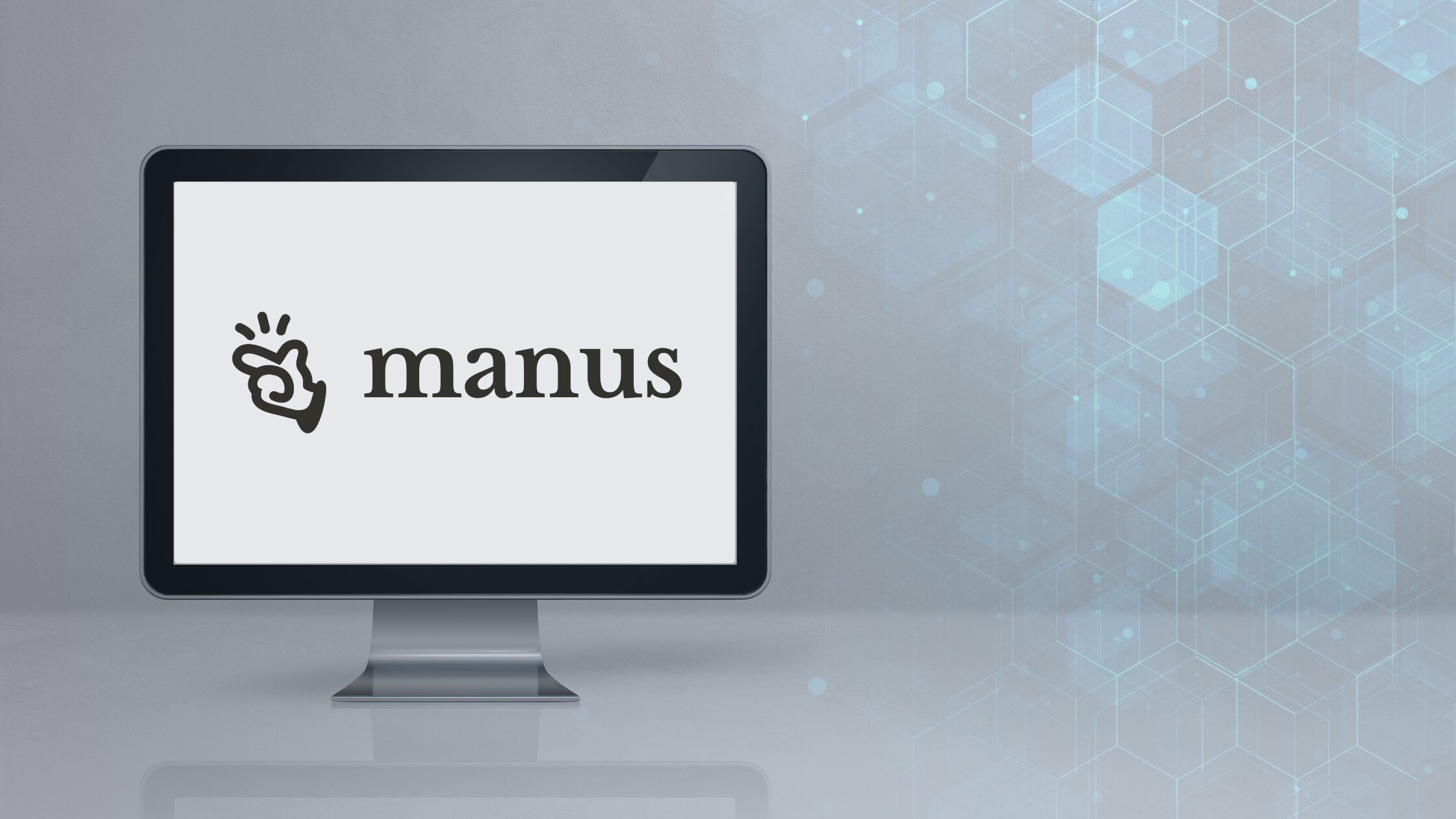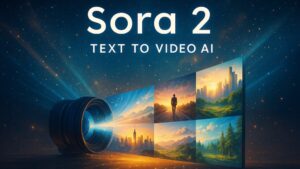この記事でわかること
・ AIエージェントとはどんな技術か
・ Manusが注目される理由と、その特徴
・ Manusの料金・できること・導入時の注意点
ChatGPTなどの生成AIを使った業務効率化が注目される中、次なるトレンドとして注目を集めているのが「AIエージェント」。
複数のタスクを自律的にこなす「任せられるAI」として、人手不足や業務の属人化に悩む企業にとっても頼れる存在になりつつあります。
中でも「Manus(マヌス)」は、ノーコードで使える・汎用性が高い・無料から試せるといった特長から、今急速に注目を集めているAIエージェントのひとつです。
とはいえ、「AIエージェントって何ができるの?」「危険性はないの?」「本当に使えるの?」といった不安や疑問を感じる方も多いかもしれません。
この記事では、話題のAIエージェント「Manus」の基本から、料金や注意点まで解説していきます。
AIエージェントとはなにか
AIエージェントとは、人間の代わりに「目的を理解し、自律的にタスクを実行するAI」のことを指します。
ChatGPTをはじめとする生成AIは、ユーザーからの指示に1つずつ反応する「受け身型」のAIです。
それに対してAIエージェントは、あらかじめ伝えた目的に基づいて、自ら必要な作業を判断・実行していく「能動型」のAIという点が大きな違いです。
たとえば「問い合わせ対応を任せる」という業務の場合、AIエージェントに依頼するだけで、入力内容の分析からデータベースとの照合、最適な回答の生成、そして対応履歴の保存といった一連の流れを、複数のサービスをまたいで自動的にこなすことができるのです。
このようなAIエージェントの進化により、これまで人手が必要だった業務の多くが自動化できるようになりつつあります。
その一方で、「実際に自社で導入できるのか?」「使いこなせるのか?」と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
実際、近年ではさまざまなAIエージェント型ツールが登場していますが、技術的な知識を前提とするものも多く、非エンジニアにとっては導入のハードルが高いと思われてきたのも事実です。
そんな中登場したのが Manus(マヌス)。
Manusはユーザーが大まかな目的を伝えるだけで、複数のAIが自律的に役割を分担しながら作業を進めてくれるという、これまでのツールとは一線を画す進化型のAIエージェントとして注目を集めています。
AIエージェントの解説や従来のAIとの違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

なぜManusが注目されているのか?
AIエージェント市場には、現在さまざまなツールが登場していますが、その中でもManus(マヌス)が注目されている最大の理由は、「ユーザーが目的を伝えるだけで、複数のAIが連携して自律的に作業を進める」というこれまでにない仕組みにあります。
このようにAIが役割分担しながら自律的に動く仕組みは、これまでのChatGPTのような「ひとつずつ指示を出すAI」とは大きく異なります。まるでチームで仕事を分担するように、AIたちが一緒に動いてくれるのがManusの特徴です。
さらにManusは中国のスタートアップ企業によって開発されたもので、国家的な支援を受けているという背景もあります。
そうした社会的な注目や期待もあり、メディアでは「次世代の業務パートナー」として紹介されることも増えてきました。
AIエージェントが個人の業務サポートだけでなく、チーム全体の生産性を底上げする存在として注目されるなか、Manusはまさにその最前線を走るツールのひとつと言えるでしょう。
Manusの特徴とできること
注目を集めるManusですが、具体的にどのような特徴があるのでしょうか。
ここではManusの強みやできることを解説していきます。
目的を伝えるだけで、タスクを自動で計画・実行
Manusの最大の特徴は、ユーザーが「何を達成したいか」という目的だけを伝えるだけで、あとのタスクをAIが自動で組み立てて実行してくれる点です。
たとえば「商品紹介のWebサイト作りたい」「競合の情報を集めて、比較レポートを作りたい」といった大まかな指示でも大丈夫。Manusはそのゴールに必要な作業を自動で分解し、順番に進めていきます。
これは、従来のAI(ChatGPTなど)のように「一つひとつ指示を出す」スタイルとは大きく異なります。
Manusは人間のアシスタントのように「目的から逆算して行動する」能動的なAIなので、業務を丸ごと任せるような使い方も可能なのです。
複数のAIが連携して同時に作業を進行
AIエージェントの中には、複数のAIがチームのように連携し、それぞれの役割を持って同時に動く「マルチエージェント型」と呼ばれるタイプがあります。
マルチエージェント型と呼ばれるAIエージェントは、1つの目的に対して複数のAIが連携し、それぞれの役割を担いながら同時にタスクを進行します。
Manusもこのマルチエージェント型のAIエージェントツールのひとつで、ユーザーが大まかな目的を伝えるだけで、必要な作業をAI同士が判断・連携しながら自動で実行してくれるのが特徴です。
たとえば「明日の営業会議の準備をお願い」と伝えるだけで、あらかじめ設定したテンプレートやシナリオに沿って、会議資料の下書きを作成し、予定をカレンダーに登録し、参加者にリマインドを送るなどの作業を自動で進めることができます。
これらの作業は、ひとつのAIが順番に処理しているわけではありません。Manusでは、目的に応じて複数のAIエージェントが役割を分担し、それぞれが自律的かつ同時並行に動く仕組みになっています。
資料作成を担当するAI、スケジュール登録を行うAI、リマインド通知を送るAIなどが、それぞれのタスクを判断しながら連携し、最も効率的な順序で作業を進めていくのです。
こうした「自律性」と「並列処理」を組み合わせ、まるで人間のチームが手分けして仕事を進めているような動きがManusの大きな特長のひとつです。
外部ツールの操作もAIがまるごと代行
ManusはGoogleカレンダーやSlack、Notion、Gmailなどの外部ツールを、直接操作する仕組みがあります。
単に情報を読み取るだけでなく、必要なデータを記録・更新したり、ツール間をまたいで処理を行ったりと、実際の作業そのものをAIが代行できるのが特徴です。
複数のツールやサービスにまたがる業務フローを、人の手を介さずに完結できる点は、Manusの実用性を支える重要な強みといえるでしょう。
定型業務や繰り返し作業をツール間連携で自動化することで、人的リソースの削減や作業精度の向上にもつながります。
進行状況や思考プロセスがリアルタイムで「見える」
AIに業務を任せるうえで気になるのが「今どんな作業をしているのか?」「本当に意図通りに動いているのか?」といった『見えにくさ』ではないでしょうか。
Manusはエージェントの思考プロセスやタスクの進行状況をがリアルタイムで可視化されるため、AIの動きをしっかり把握することができます。
たとえば「情報収集中」「メール作成中」など、今どのステップを処理しているのか、どこまで完了しているのかが一覧で表示される画面設計になっており、作業の透明性が高いのです。
処理中にエラーが発生した場合も、どのタイミングで何が原因だったのかを画面上で確認できるため、トラブル対応や再実行もスムーズに行うことができます。
ブラウザを閉じても作業を継続できる安心設計
何かの作業をパソコンで実行しているとき、「画面を閉じたら止まってしまうのでは?」と不安になったことはないでしょうか。
AIツールや自動化システムを使っているときはなおさら、自分が見ていない間もきちんと動いているのかが気になるものです。
Manusは一度タスクを指示すれば、ブラウザを閉じたりPCを離れたりしても、作業をバックグラウンドで継続してくれます。
たとえば夜のうちに資料作成や調査業務を任せておけば、翌朝には完了している。こうした『放っておける安心感』は、他のAIツールにはない強みのひとつです。
つきっきりで監視しなくても自動で仕事が進むこの仕組みは、日々の業務に追われがちな少人数のチームや、限られたリソースで動いている現場にとって心強い味方になるはずです。
また定期的なデータ取得やシステム監視など、人が張りついて対応していた定常業務の自動化にも活用できる点は、大きな魅力と言えるでしょう。
自動化の第一歩に!定番業務のテンプレートが豊富
Manusには、よく使われる業務フローがあらかじめテンプレート(Manus Playbook)として用意されており、ゼロからシナリオを構築する必要はありません。
このテンプレートとは、特定の目的を達成するために、AIエージェントがどのような手順で動くかをあらかじめ設定した「自動化フローのひな形」のようなものです。
たとえば「フォームからの問い合わせ → 内容を要約 → 担当者にSlackで通知」といった一連のプロセスが、あらかじめ構築された状態で提供されています。まるでアプリケーションのように、そのまま使える感覚です。
ユーザーはこのテンプレートをベースに、自社の業務に合わせて内容をカスタマイズするだけ。
専門的な知識がなくても、すぐにAIエージェントによる業務自動化をスタートできます。
さらに、他のユーザーが作成・公開しているテンプレートも利用可能です。
「まずは試してみたい」「似たような業務を参考にしたい」といったニーズにも柔軟に応えられる点が、多くのユーザーに支持されている理由のひとつです。
Manusの料金プラン
Manusの最新料金プランは、無料プランと3つの個人向け有料プラン(Basic/Plus/Pro)、およびチーム向けのTeamプランで構成されています。
プランはクレジット制となっており、クレジットの付与量や機能制限に応じて段階的に選ぶことができます。
| プラン名 | 月額料金 | 初回クレジット | 月間クレジット | 日次クレジット | 同時実行数 |
| 無料プラン | 無料 | 1,000 | 0 | 300 | 約1(推定) |
| Basicプラン | 月次払い:$19 年契約:$16 | 1,900 | 1,900 | 300 | 2 |
| Plusプラン | 月次払い:$39 年払い:$33 | 3,900 | 3,900 | 300 | 2 |
| Proプラン | 月次払い:$199 年払い:$166) | 19,900 | 19,900 | 300 | 2 |
Teamプランは最低5ユーザーから契約可能とされていて、導入を検討する際は直接問い合わせが必要です。
2025年10月時点の情報です。
料金プランや内容は今後アップデートされる可能性があります。最新の詳細は Manus公式サイト をご確認ください。
Manusを使う上で知っておきたい4つの注意点
AIエージェントは非常に便利な技術ですが、まだ新しい領域ということもあり、いくつか注意しておきたいポイントがあります。
特に業務で活用する際には、以下のようなリスクについて把握しておくと安心です。
データプライバシー・情報漏洩
AIに業務を任せるには、社内データや顧客情報などの取り扱いが発生するケースもあります。
こうした情報が外部に送信されたり、想定外の使われ方をする可能性がゼロとは言えません。
予期しない/不正確な動作
AIが自律的に動くという性質上、時に意図しない回答をしたり、不完全な作業を行ってしまうケースもあります。
過信せずに人のチェックを前提とした使い方が大切です。
制御の透明性・ブラックボックス性
AIがどう判断して動いているのかを人が完全に把握するのは難しく、「なぜこう動いたのか?」がわからない場合もあります。導入時には、ログの確認や動作ルールの設計も検討しておきましょう。
法的な責任の所在
AIが業務上の意思決定を行った場合、それが正しくなかったときに誰が責任を持つのか曖昧になる場面もあります。
たとえばAIが自動で作成した契約書や提案文書に誤りがあった場合など、実務にも直結するケースが考えられます。
こうしたリスクを避けるためには、人の最終確認プロセスを残すことや、AIの判断範囲を限定するなど、明確なルールを設けて運用することが重要です。
なおAIの活用に関しては、すでに各国で倫理やガバナンスの観点から一定のガイドラインが示されています。
日本国内でも、企業がAIを導入する際の参考となる枠組みは徐々に整いつつあります。
とはいえAIの進化スピードは非常に速く、現行の法制度やルールだけでは対応しきれない部分も多く残っています。
AIの行動に誰が責任を持つのかといった法的な論点は、今後の技術的な成熟や制度整備とともに段階的に整理が進んでいくと考えられます。
まとめ
AIエージェントはまだ新しい技術のため、セキュリティや透明性の面で不安が残る部分もあります。
ただ、それ以上に得られる業務効率化のメリットも大きく、うまく活用することで心強い味方となる技術でもあります。
利用者は「法的に問題がないか」だけでなく、「それは本当に正しい使い方か?」を意識しながら主体的に判断し、自社の業務や立場に合った形で慎重に取り入れていくことが大切です。
とはいえ、難しく考えすぎると、なかなか最初の一歩が踏み出せなくなってしまうもの。
まずは、自分が把握できる範囲から小さく試してみることから始めてみませんか?
\ AI導入・活用でお悩みの中小企業の方へ /
「AI導入したいけど、何から始めればいいの?」「最適なツールや活用法がわからない…」
そんなお悩みはありませんか?
ePla運営会社では、中小企業の業務に合ったAIツールの導入方・活用方法について
無料でご相談を承っています。
導入前に気軽に話せる相談窓口として、ぜひご活用ください。