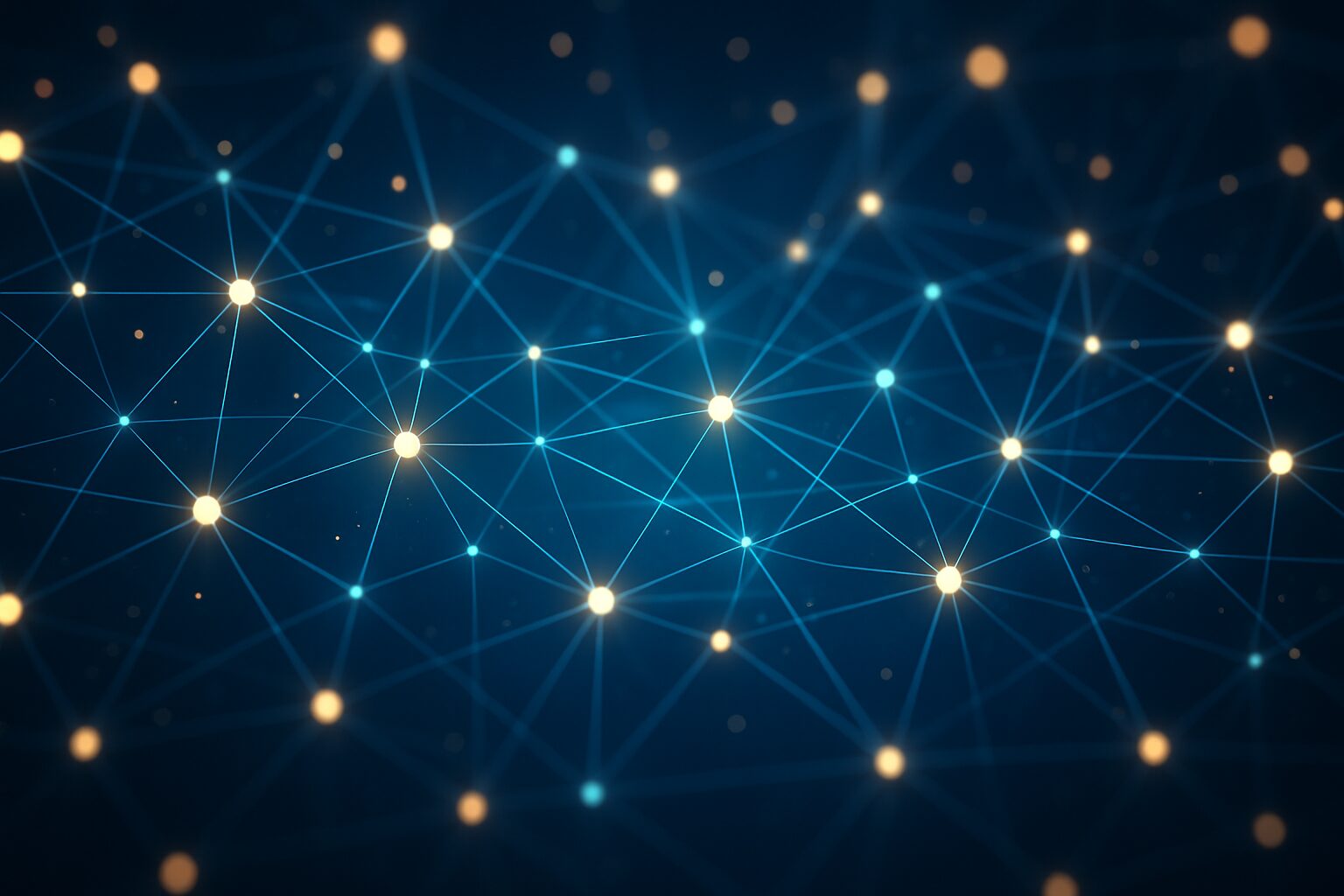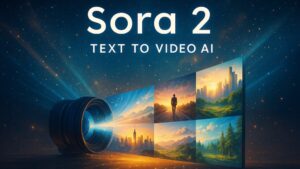この記事でわかること
・ MCP(Model Context Protocol)とは何か
・ MCPが注目されている理由
・ MCPの強みと特徴
・ 指摘された脆弱性とその背景
AI活用の最新キーワードとして注目されている「MCP(Model Context Protocol)」。
MCPは例えていうと 「AIに社内の事情を理解させる仕組み」 のようなものです。
マニュアルや商品データ、業務ルールといった『文脈』をAIに渡すことで、より実務に即した活用が可能になります。
とても便利な仕組みですが、一方で最近は脆弱性が報告されニュースで知ったという方も多いのではないでしょうか。
本記事では、まずプロトコルとは何か?という基本から解説し、MCPが生成AIの世界でどのように活用されるのか、そして指摘されている課題についても取り上げます。
MCPやプロトコルを理解しておくことで、AI活用の幅は大きく広がるはずです。
MCPとは
AI活用の話題で最近よく耳にするようになった、MCP(Model Context Protocol)。
MCPは、AIに文脈を伝えるための仕組み のことです。
通常のAIはとても賢いものの、私たちの会社のルールや商品情報、あなたの社内で使われている独自の言葉までは知りません。
そのため「一般的な答えは返してくれるけれど、うちの状況に当てはめるとちょっと違う…」というケースがよくあります。
MCPは、このギャップを埋めるために考えられたプロトコルです。
マニュアルや商品データベース、業務ルールといった情報を共通のルールに従ってAIに渡すことで、まるで「社内の事情を知っているAIアシスタント」のように使える仕組みです。
プロトコルとは
プロトコルとは、コンピュータ同士がやり取りするときの共通ルールのことです。
たとえば、私たちが普段Webサイトを見るときに使っている「HTTP」や「HTTPS」もプロトコル。
ブラウザとサーバーが「このルールで通信しましょう」と決めているからこそ、世界中どこからでも同じWebページを表示・閲覧することができます。
つまりプロトコルがあることで、異なる環境やシステム同士でも正しくやり取りが可能になります。
MCPも同じように、AIと外部データをやり取りするためのルールを定めた仕組みなのです。
MCPが注目される理由
MCPが大きな注目を集めているのは、単に「新しい技術だから」という理由ばかりではありません。
これまでの生成AIは便利ではあるものの、社内ルールや最新の業務データには対応できず、実務にそのまま使うには解消すべきいくつもの課題を抱えていました。
たとえば、実際の業務に適した動きをさせるためにはPythonなどでプログラミングを行ったり、専用の仕組みを開発してAIとデータをつなぐ必要があったりと、それらの課題は多くの企業にとって大きなハードルとなっていたのです。
そこで新たに登場したプロトコルがMCPです。
MCPを利用すれば自社の情報をAIに安全かつ統一的に渡せるようになり、AIがより実務に寄り添った回答や提案を行える可能性が広がります。
つまりMCPは「一般的な知識しか持たないAI」と「自社固有の事情を踏まえたAI」との間にあるギャップを埋め、AIを実務で本格的に活用できるようにする技術として期待されているのです。
従来のAI活用との違い
現在も多くの場面では、必要な情報をその都度コピー&ペーストしてAIに教えるスタイルが一般的です。
たとえば商品情報や社内マニュアルを一部抜粋してAIに入力し、「この内容をもとに回答して」と指示する。そんな使い方が中心になっています。
しかしこの方法では、情報を更新するたびに同じ作業を繰り返す必要があり、データやマニュアルの量が増えるほど作業負担が膨らむという課題があります。
またAIに渡せる情報量や処理できるデータ量には上限があるため、一部の情報が反映されなかったり文脈が途切れたりすることもあります。
さらに登録データの更新が反映されず古い情報を参照してしまうなど、運用面での課題も少なくありません。
こうした課題を軽減するため、ChatGPTの「GPTs」を活用する方法もあります。GPTsにあらかじめ複数のマニュアルやFAQを読み込ませておくことで、手作業による情報入力の手間を減らすことができるためです。
ただし、これはChatGPTの専用環境内で完結する仕組みであり、他のAIや外部システムとの連携には対応していません。
一方、MCPは複数のAIや外部システムと接続できる共通のプロトコルです。
どのAIモデルを使っても同じ方法でデータにアクセスできるようにすることで、環境を選ばず活用できるのが特徴です。
たとえば社内マニュアルや商品データベース、FAQなどを一元的に管理し、必要なときにAIが最新情報を参照できるようになるため、結果として「情報を人が毎回教え込む」という手間を大幅に減すことができるのです。
AIモデルに依存しない共通ルール
MCPの大きな特徴である「AIモデルに依存しない共通ルール」について、もう少し詳しく見ていきましょう。
多くの企業ではChatGPTやClaude、Geminiなど、さまざまな生成AIを業務で活用しています。
それぞれに得意分野や特徴があり、部門ごとに異なるAIを使い分けることも珍しくありません。
しかし一方でAIごとに設定方法や連携の仕組みが異なるため、同じデータを活用するにも環境ごとに別々の調整やカスタマイズが必要になるという課題がありました。
たとえばChatGPTではGPTsを使ってマニュアルを読み込ませることができても、その設定をClaudeやGeminiにそのまま引き継ぐことはできないのです。
対応させるためには各AIに合わせてデータの構造や接続方法を変える必要があり、運用や開発の手間が発生してしまいます。
MCPはこうしたAIごとの違いを吸収し、どのAIモデルでも共通のルールでデータを扱えるようにするプロトコルです。
MCPに対応していればAIの種類に関係なく同じ方法で外部データやシステムと連携できるため、環境を選ばず柔軟に運用できます。
たとえばChatGPTからClaudeへAIモデルを切り替えたとしても、MCP経由で同じ社内データにアクセスして同様の回答を得ることが可能になるのです。
さらに今後新しいAIモデルが登場した場合でも、既存の仕組みを大きく変えずに導入できるというメリットも。
このように、MCPは『AIの乗り換えリスク』を減らし、データ活用の継続性を高める役割も果たします。
企業にとっては、「どのAIを選ぶか」よりも、「AIをどう活用するか」に集中できる環境を実現できる点がMCPの大きな価値といえるでしょう。
MCPで指摘されている脆弱性
MCPはAIと外部データをつなぐための革新的な仕組みとして注目を集めている一方で、2025年に入ってからいくつかの脆弱性(ぜいじゃくせい)が報告されて話題となりました。
特に影響が大きいといわれているのは、MCPの関連ツールである「mcp-remote」および「MCP Inspector」における脆弱性です。
※本章に記載している内容は2025年9月時点の情報です。
確認されている主な脆弱性
現時点で報告されている代表的な脆弱性は、次の2つ。
- mcp-remote のリモートコード実行(RCE)脆弱性
- MCP Inspector のリモートコード実行(RCE)脆弱性
それぞれ、どのような問題だったのかをみていきましょう。
2025年7月、MCP関連ツールのひとつであるmcp-remoteにおいてリモートコード実行(RCE)の脆弱性が報告されました。
この問題は、mcp-remote が信頼できない MCP サーバーに接続した場合に、外部から不正なコマンドを実行される可能性があるというものです。
この脆弱性はあくまで特定の条件下で悪意あるサーバーに接続した場合に限られ、通常の利用環境で直ちに影響を受ける可能性は低いとされています。
同時期、MCP Inspectorにおいても深刻な脆弱性が発見されました。
この問題は、MCP Inspector のクライアントとローカルサーバー間の認証やCSRF(クロスサイトリクエストフォージェリ)対策が不十分だったことに起因します。
その結果、ローカル環境で MCP Inspector を実行している状態で悪意あるJavaScriptを含むWebサイトにアクセスすると、外部のサイト経由で不正なコマンドが送信されて任意のコードが実行される恐れがありました。
いずれの脆弱性もすでに修正版のアップデートが公開されており、Anthropic(Claude開発元)やセキュリティベンダーが迅速に対応を行っています。
またMCPを利用する開発者向けには、公式リポジトリでセキュリティガイドラインやパッチ適用の手順が案内されています。
仕組み自体が危険ではない理由
MCPで報告された脆弱性はMCPという仕組みそのものが危険というよりも、新しい技術が急速に広まる中で運用やセキュリティのリテラシーが追いついていないことに起因する部分が大きいといえます。
MCPはAIと外部システムをつなぐための共通ルール(プロトコル)として設計されています。
つまり、AIが外部のデータやツールに安全にアクセスするための土台のような存在です。
しかしその一方でまだ登場して間もない技術であるため、開発者や利用者の間で「どのように設定・運用すれば安全なのか」という共通理解やガイドラインが十分に整っていないのが現状です。
実際に報告された脆弱性の多くは、構成ミスや認証の設定不備、アクセス範囲の誤設定といった実装・運用上の課題に起因しています。
たとえば、検証目的で立てたMCPサーバーをインターネット上で公開していたり、信頼できない外部サーバーに接続してしまったりといったケースが典型です。
つまり、MCPの仕組み自体に致命的な欠陥があるわけではなく、「新しい仕組みだからこそ、正しく使うためのルール整備が追いついていない」という段階といえるでしょう。
今後AIベンダーやセキュリティコミュニティによるガイドラインの整備が進むことで、MCPはより安全で信頼性の高い技術基盤へと成熟していくと考えられています。
まとめ
MCP(Model Context Protocol)は、AIと外部システムをつなぐための新しい共通ルールとして登場した技術です。
従来のように情報をその都度AIに教え込む必要がなくなり、最新データを安全に扱いながら、より実務に即したAI活用を実現できる点が大きな特徴です。
MCPはまだ発展の途中にありますが、AIと業務データをより深く結びつける基盤技術として大きな期待が寄せられています。今後MCPの標準化・安全対策が進めば、企業が安心してAIを業務に取り入れられる「新しいインフラ」となっていくでしょう。
AIを「社内で本当に使える存在」に変えていく上で、MCPは今後のAI活用を考えるうえで欠かせないキーワードになりそうです。
\ AI導入・活用でお悩みの中小企業の方へ /
「AI導入したいけど、何から始めればいいの?」「最適なツールや活用法がわからない…」
そんなお悩みはありませんか?
ePla運営会社では、中小企業の業務に合ったAIツールの導入方・活用方法について
無料でご相談を承っています。
導入前に気軽に話せる相談窓口として、ぜひご活用ください。